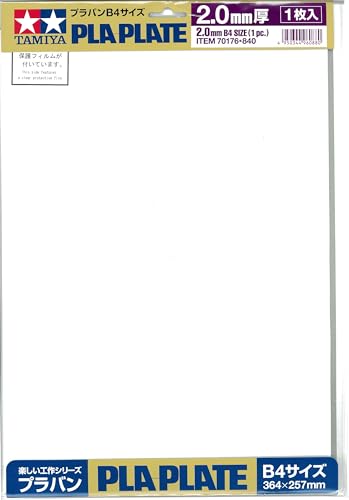釣りを始めるなら、ランディングネットは必ず持っておきたいアイテムの一つです。そんなランディングネットを自分で編むことはできるのでしょうか?今回、釣りラボでは、ランディングネットの編み方を徹底解説します。
そもそもランディングネットとは?

ランディングネットは、魚をすくう網のことです。
タモ網とも呼ばれます。
特に大物がかかったときには必須のアイテムです。
ランディングネットの選び方
ランディングネットは、形や素材などが製品によって異なります。
選ぶポイント1:フレームの形
まず、フレームの形は丸型と先が広がったひょうたん型の2種類です。
丸型は強度が高いというメリットがあります。
一方のひょうたん型は魚をすくいやすいのが利点です。
選ぶポイント2:ネットの素材
ネットの素材はナイロンとラバーが代表的です。
ナイロンは水切れがよく、魚を取り込みやすいですが、魚の体を傷つけやすくリリースする釣りには向きません。
ラバーは魚の体を傷つけにくいという特徴がありますが、ナイロン製に比べ価格が高いというデメリットがあります。
選ぶポイント3:柄の長さ
柄の長さも様々で、水面までの距離によって使い分ける必要があります。
また、折り畳み式やショルダーベルト付きのものは持ち運びに便利です。
各メーカーから様々なランディングネットが販売されていますので、釣り場やターゲットに合わせて選びましょう。
ランディングネットの使い方
ランディングネットを使うタイミングは、水面に上がってきた魚が弱っておとなしくなった時です。
水面にそっとランディングネットを入れます。
必ず魚の頭側にネットを入れるようにしてください。
この時ラインは張ったままにせず、緩めるようにするのがポイントです。
ランディングネットは水中に入れたらなるべく動かさず、竿を操作して魚の方をネットの中に誘導するようにしましょう。
水面から距離がある場合には、ネットの柄を手元の方から縮めていきます。
柄が長いまま真上に上げると、魚の重みで柄が折れることがあるからです。
ランディングネットは自分で作れる?メリットは?

ランディングネットは自作することが可能です。
手間がかかり、編み方に慣れるまでは時間もかかりますが次のようなメリットがあります。
コストが抑えられる
ランディングネットの材料となるクレモナ糸は200gで1500円ほどで販売されています。
200gの糸があれば数枚のネットが作れるのでコストパフォーマンスはバツグンです。
必要な道具も数百円で買えるものばかりなので、揃えるのにあまり費用がかかりません。
自分好みのデザインが選べる
ランディングネットを編むのに慣れてきたら、デザインをカスタマイズして自分好みのネットを作ることができるようになります。
デザインといってもネットの形は網目の数で決まるので、作りたい形に合わせて網目を増やしたり減らしたりするだけで好きな形に編むことができます。
また、染料を使って糸を染めれば好きな色のネットが作れます。
染料は種類が豊富で色を混ぜることもできるので、グラデーションにするなど市販品にはないオリジナルカラーができるのが魅力です。
補修して使い続けることができる
使い続けるうちにネットの一部が切れてしまっても、編み方を知っていれば修理することができます。
破損の状態によっては新しいネットを編んで付け替えてもよいでしょう。
フレームさえ壊れなければ、ネットだけ付け替えて使い続けることが可能なのです。
ランディングネットを編む際に必要な道具

では実際に、ランディングネットを編む際に必要な道具とおすすめの商品をご紹介します。
ランディングネットを編む際には、以下のようなものを用意しましょう。
クレモナ糸
クレモナ糸は、ビニロンという合成繊維の糸で、強度が高く変質しづらいという特徴があります。
ランディングネットを編むのに使われるのは2号〜8号の太さのもので、6号以上の糸は大型魚用のランディングネットに使用します。
【まつうら工業】クレモナ製 3号
100g巻きになっていて、長さは300mあります。
作るネットの大きさにもよりますが、1巻きで5枚ほどのランディングネットを作ることができます。
【瓢箪印】クレモナ糸 4号

200g巻きで長さは約420mです。
ランディングネットを編む以外にも、園芸や日曜大工などの用途があります。
染色剤
染色剤は、簡単に糸を染めることができる、ダイロンが便利です。
色が豊富で、染めるものの種類によって様々なものがあります。
お気に入りの一色を探してみてください。
【ダイロンジャパン】DYLONマルチ8色カラーセット

ダイロンマルチのお得な8色セットです。
混色やグラデーションにして、オリジナルカラーのランディングネットを作ってみてはいかがでしょうか。
網針(アバリ)
網針(アバリ)は、使うクレモナ糸や、網目の大きさに合わせて3種類ほど揃えておくと安心です。
樹脂製と木製があり、木製の方が高価です。
【リバーピーク(river peak)】網針

プラスチック製の網針です。
2号、7号、8号の3種類があります。
練習用の最初の1本にいかがでしょうか。
コマ板
コマ板は、網目の大きさを揃えるために使います。
プラスチック製の板をカッターナイフ等で必要な幅に切り取って使う人が多いです。
フレームをつけるための糸・糸通し
フレームの穴にネットを通すのに道具が必要になります。
スレッダー(糸通し)があると便利ですが、余っている釣り糸を使用することもできます。
【ささめ針】天秤仕掛便利糸
フレームにネットを固定する糸として使用します。
糸自体に張りがあるので、フレームの穴にランディングネットの網目を通すのに道具が必要ありません。
ランディングネットの基本の網目の編み方
ランディングネットを編む際に使う基本の網目の編み方を2種類ご紹介します。
言葉だけでは分かりにくいところもあるので、編み方の動画も参考にしてください。
結び方1:本目結び
本目結びは、結び目2つで一目になります。
見た目が綺麗な編み方です。
本目結びの編み方の手順は、以下の通りです。
太い糸を使って本目結びの編み方を実演している動画です。
分かりやすいので参考にしてください。
結び方2:蛙又結び
蛙又結びは、本目結びより簡単にできる結び方です。
ランディングネットの2段目以降を編むのに使用します。
蛙又結びの手順は、以下の通りです。
言葉での説明だと難しく感じますが、動画で見ると簡単なのが分かります。
本目結びよりも手順が少なく、慣れれば速く編むことができます。
4分あたりから蛙又結びの編み方の解説が始まります。
自作ランディングネットの編み方

自作ランディングネットの編み方には、筒になる部分から編む方法と、底を先に編んでから筒部分を編む編み方があります。
ここでは簡単な編み方として、フレームに取り付ける部分から編み始めて筒部分を編み、網目を減らして袋状にする方法をご紹介します。
筒部分を編む
筒の部分を編むために必要なものは以下の通りです。
準備は、以下の順番で行いましょう。
筒部分の編み方の手順は以下の通りです。
減らし目をして網の底を作る
筒部分が必要な長さになったら、減らし目をして網の底を作っていきます。
減らし目の編み方は、蛙又結びで最初に網目をすくう際に2目一緒にすくうだけです。
こうすることで目の数が減って筒から袋状になります。
全ての目で減らし目をすれば先細りの形になり、数目おきに減らし目をすれば緩やかなカーブを作ることができます。
お好みで編み方を調節してください。
減らし目を繰り返して網目が5〜6目になったら全ての目に編み糸を通して引き締め、底を閉じます。
フレームをつける
ネットが編みあがったら、ネットをフレームに取り付けます。
フレームの穴にネットを通して別糸で固定します。
別糸に使用するのは、ランディングネットを編むのに使用したクレモナ糸で構いません。
7:30くらいから、ネットをフレームに付ける作業の解説をしています。
釣り糸を使用してネットをフレームの穴に通す方法です。
ランディングネットの編み方のまとめ

いかがでしたでしょうか?
今回、釣りラボでは、「ランディングネットの簡単な編み方を解説!網目の種類や減らし目の方法も紹介」というテーマに沿って、
といったことをご紹介してきました。
他にも、釣りラボでは、釣りに関連する様々な記事をご紹介しています。
もし、釣りに関してまだ知りたいことがあれば、サイト内検索をご利用いただくか、ぜひ関連する他の記事をご覧ください。
最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます