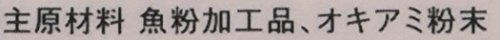【人気の魚図鑑】今回、釣りラボでは、メイチダイの特徴、生態、呼び名、生息地、値段相場を徹底解説した上で、メイチダイの味、おすすめのレシピ、人気のお店、釣り方、さばき方などをご紹介します。
メイチダイとは?その特徴・生態をご紹介
メイチダイは、フエフキダイ科メイチダイ属に分類される、成魚で最大40cmほどになる魚です。
体高は高く、体形は平たい楕円形をしており、体の色は白っぽい銀色をしています。
体色の銀色は、生息地により異なることがあり、金色や赤味がかった色をしていることがあります。
メイチダイの特徴は、黒い大きな目と体に薄く黒いラインが数本あることです。
この黒いラインが目の部分にもかかっているため、メイチダイという名前が付けられました。
稚魚、幼魚では、この黒いラインが鮮明ですが、成長するにつれて薄くなっていきます。
幼魚は、浅瀬で生息しているので、ダイビングする人にとっては、馴染みのある魚です。
メイチダイの呼び方
メイチダイの呼び方を確認しましょう。
漢字名
メイチダイの漢字名は「目一鯛」となります。
メイチダイの特徴である縞模様が目を突き抜けて見えることが由来です。
別称・別名
メイチダイは、水揚げ地により別称・別名があります。
代表的なもので、愛知県では「イチミダイ」、三重県尾鷲市では「メイチ」、宮崎県では「メテ」などがあります。
英語・外国名
英語名・外国名は「Nakedhead」「Grey Large-eye Beam」となります。
やはりメイチダイの特徴でもあるeye(目)という単語が使われています。
学名
学名は「Gymnocranius griseus」です。
メイチダイの生息地
日本では、千葉県・新潟県より南の沿岸部、琉球列島に生息しています。
水深100m以下の浅瀬の砂、岩礁のある海底付近で、小魚、エビやカニなどの甲殻類を捕食しながら生活しています。
夏から秋にかけて、1mm弱の分離浮性卵を産卵します。
メイチダイは、静岡県にある下田海中水族館(2020年5月時点)、三重県の鳥羽水族館(2020年6月時点)で見ることができます。
メイチダイが漁獲される地域
メイチダイは、定置網、底引き網で漁獲され、主に長崎、鹿児島、三重などで水揚されます。
漁獲量が少ないことと非常に味が良いことから、都市部では高級魚として知られています。
鯛より知名度はありませんし、見た目も地味な印象ですが、鯛よりも美味しいと評判の魚です。
メイチダイの値段・相場価格
メイチダイの相場価格は、その年の水揚げ量によりますが、平均1kg当たり2000円から5000円です。
旬である夏になると、漁獲量が増えますので安くなります。
メイチダイを使った料理・食べ方

メイチダイは、産地以外ですと、滅多に店頭に並ぶことのない高級魚です。
どのように食されているのか、調べてみました。
どんな味がするの?臭いに癖がある?
メイチダイは白身魚ですが、比較的脂が多い身をしています。
主に皮と身の間や内臓のまわりに脂がついています。
そのため、鯛のように淡泊な味ではなく、脂の甘味と濃厚さがあります。
ただし、メイチダイの目には、臭い成分が含まれています。
調理する際に目を傷つけると、癖のある臭いがするので注意してください。
他の部分に臭いが移って、せっかくの料理が台無しになってしまいます。
栄養素・カロリー
メイチダイは低カロリーで、タンパク質、不飽和脂肪酸などの栄養が豊富です。
メイチダイには脂が多いですが、魚の脂は不飽和脂肪酸なので、血中コレステロールを減らす働きがあります。
旬な時期・季節
メイチダイの旬な時期は夏から秋の季節です。
特に産卵前が、一番脂を蓄えて美味しい時期となります。
おすすめ人気のレシピ・調理方法
高級魚と評されるメイチダイのレシピを集めましたので、是非、挑戦してみてください。
刺身
刺身として食べる時には、寄生虫アニサキスがいないかどうか、目視でしっかり確認しながら切り分けてください。
メイチダイの目を傷つけてしまうと臭いがするので、注意しましょう。
炙り刺し
メイチダイを刺身に切り分けて、皮を付けたまま焼いて食べます。
バーナーがない場合は、串に刺して、ガスコンロの火で直接炙っても良いでしょう。
皮に焦げ目がついたら、出来上がりです。
寿司
メイチダイを握り寿司にしても、白身の魚とは思えない濃厚な味が楽しめます。
寿司飯を準備し、刺身用のメイチダイを上にのせるだけで出来上りです。
メイチダイを楽しめる人気のお店・レストラン
東京の東銀座駅近くにある羽田市場ギンザセブンでは、朝釣れた新鮮な魚を取り寄せています。
旬の季節である夏には、メイチダイに出会うチャンスがあるでしょう。
メイチダイにおすすめの釣り方・仕掛け

メイチダイを釣るには、フカセ釣りとルアーを使ったタイラバという釣り方があります。
タイラバとは、ヘッド(丸いオモリ)にスカート、ネクタイと呼ばれるパーツをぶら下げて釣るルアーフィッシングです。
本来はタイを釣るための釣り方でしたが、他の魚やメイチダイを釣ることができます。
釣り方は、仕掛けを海に落として、仕掛けが海底に着いたら巻き上げます。
アタリがあっても、一定の速度で巻き上げるのがポイントです。
タイラバは手軽に楽しむことができるため、タイラバ専用のルアー、ロードなどがたくさん販売されています。
メイチダイ釣りにおすすめの釣竿・ロッド
メイチダイを釣るのであれば、2m前後のタイラバ専用のロッドがおすすめです。
代わりに柔らかい船竿を使っても良いです。
メイチダイ釣りにおすすめのリール
メイチダイ釣りには、小型の100〜200番のサイズで、両軸にリールがあるタイラバ専用リールがおすすめです。
ハンドルには、ダブルとシングルの2つのタイプがあります。
初心者には、巻きやすいダブルハンドルが扱いやすいです。
メイチダイ釣りにおすすめのルアー(タイラバ)
タイラバの重さは、水深と同じ数字が目安となります。
タイラバのルアーには、固定式と遊動式がありますが、最近は遊動式タイプが人気です。
ヘッドの部分と下に付いているラバーの部分が固定されていなく、自由に動かせるようになっています。
【メジャークラフト】タイノミ 60g〜160g
いろんな重さのタイラバを取り揃えておくと良いです。
このタイラバはヘッドを交換することもできます。
メイチダイ釣りにおすすめの釣り餌
メイチダイをフカセ釣りで狙う場合には、オキアミなどの撒き餌が必要です。
メイチダイの締め方・捌き方

メイチダイに限らず、魚が釣れた場合は、適切な方法で締めて自宅に持ち帰りましょう。
メイチダイの締め方
釣りに行く前に、しっかり魚の締め方をマスターしましょう。
締め方が悪いと、メイチダイの鮮度が落ちてしまいます。
但し、目を傷つけると臭くなってしまうので、十分注意してください。
捌き方(さばき方)・切り方
メイチダイを刺身にするには、右身、左身、中骨の3つに分けます。
3枚おろしはどの魚でも同じやり方ですので、下記の動画を参考にしてください。
また、頭以外の残った部分は捨てずに、是非、出汁を作ってみてください。
メイチダイの基本情報まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回、釣りラボでは、「【メイチダイの基本知識】レシピ・旬な時期・釣り方・さばき方を解説!」というテーマに沿って、
といったことをご紹介してきました。
他にも、釣りラボでは、釣りに関連する様々な記事をご紹介しています。
もし、釣りに関してまだ知りたいことがあれば、サイト内検索をご利用いただくか、ぜひ関連する他の記事をご覧ください。
最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます